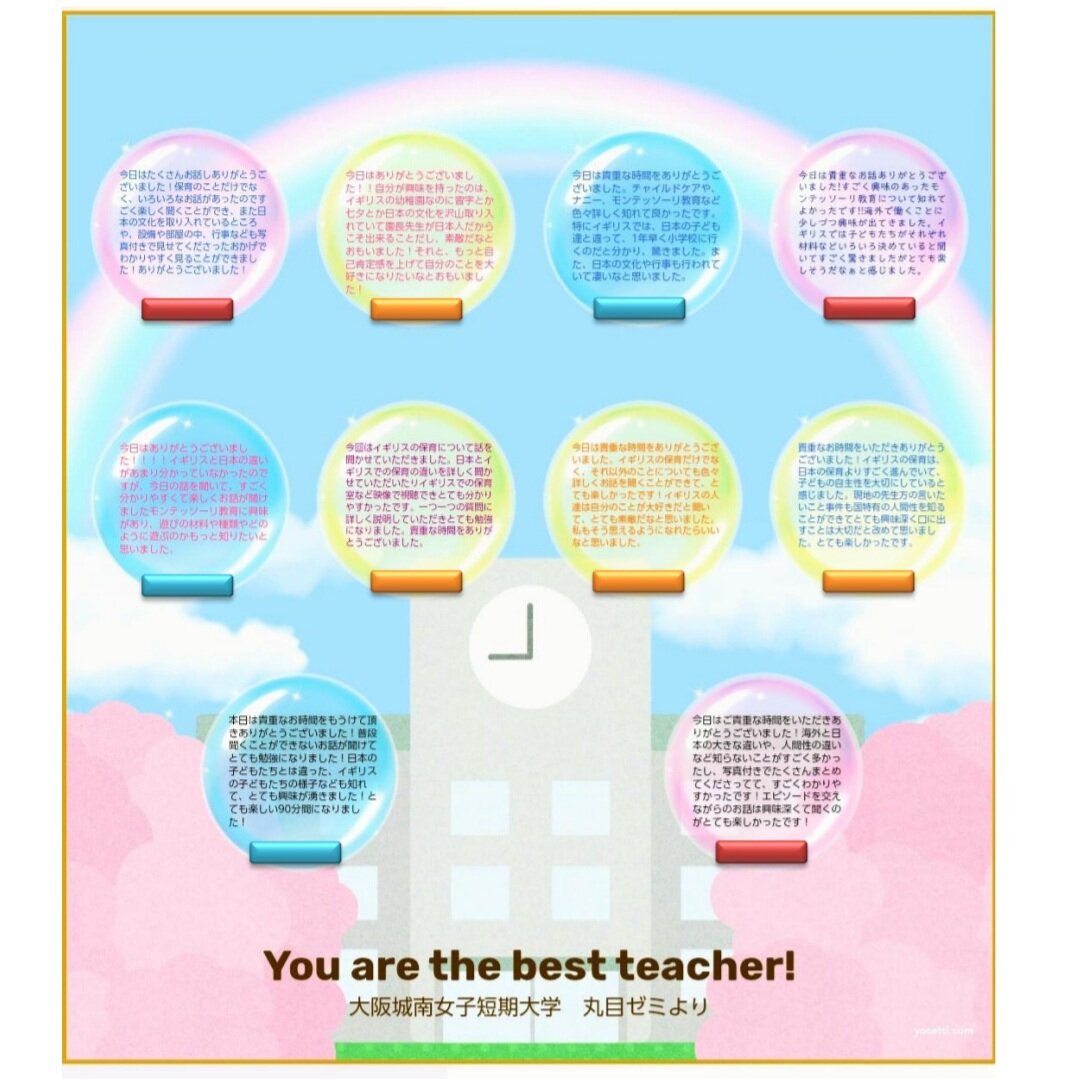シリーズ【イギリスの幼児教育】 第9回:乳幼児期に形成される親子の絆の大切さを提唱した ジョン・ボウルビィ(その3)
前々回は、イギリス人精神科医のジョン・ボウルビィ(John Bowlby, 1907–1990)の、生い立ちや初期の頃の経歴について、そして、前回は、「アタッチメントセオリー」について詳しく紹介しました。今回は、それが、幼児教育の現場や社会に、どのように反映されているのかを探求していきます。
ボウルビィの「アタッチメントセオリー」は、幼児教育のベースとなる概念として、世界中の保育現場で幅広く取り入れられています。
イギリスの幼児教育要綱EYFSでは、アタッチメントセオリーと関連させて、
一人一人の子どもの愛着行動を理解して、常に子ども中心の保育を心掛けること
保育園が子どもの安全基地となるように、保育士は子どもとの信頼関係を築くこと
親と離れている時に、一番身近で寄り添ってくれるキーパーソンと呼ばれる担当者制度を導入すること
を義務付けています。
今は共働きの家庭も多く、子どもが小さいころから保育園に預けるケースも多くなっています。ですから、親がいない間も、子どもが安心して穏やかに保育園で過ごせるように、担当制や担当保育士の果たす役割が、ますます重要視されているのです。
日本でも、子ども庁が描く「幼児期までのこどもの育ちに関わる基本的なビジョン」にも、乳幼児の育ちにはアタッチメント(愛着)の形成と豊かな「遊びと体験」が不可欠という項目が、ビジョンの1つに挙げられています。
また、子どもの頃に十分な愛情を注がれなかったことによって引き起こされる「愛着障害」という言葉も、ひんぱんに耳にするようになってきました。最近では、児童虐待やネグレクトなどの極端なケース以外にも、一見普通の家庭で育った人にも、愛着障害を抱えている人が多くいることがわかり、日本では人口の3割超にも相当するとも言われています。
このように、最近ますます乳幼児期の「愛着」の重要性が見直され、ボウルビィが唱えた「アタッチメントセオリー(愛着理念)」は、発表から半世紀経った今も、子育てや幼児教育向けだけでなく、社会的にも注目され続けています。
おすすめ情報
関連の話題
海外保育のトピックを検索